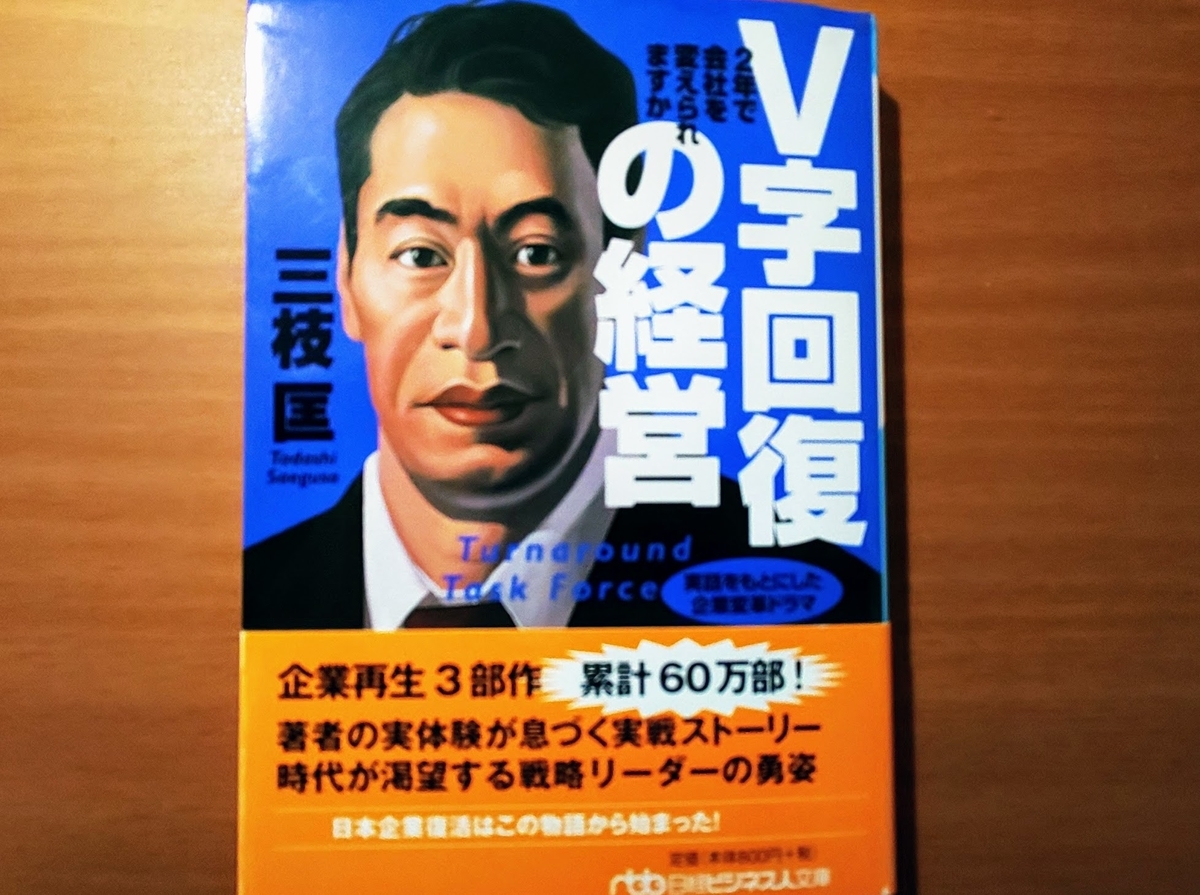
【1.本書の紹介】
著者は、現在(株)ミスミグループ本社のシニアチェアマン(企業功績を称えるポジション)で、経営立て直しのプロフェッショナルであり、自身が務める会社(ミスミ)を急成長させた凄腕経営者です。
この物語は、著者が(株)コマツの「産機事業本部」の事業再生に携わった経験をベースとして書かれています。
実体験をベースとしているだけあり、この物語は臨場感に溢れ、登場人物の描写が非常にリアルで、それぞれ違う立場の人々のその心の変化までがよく伝わってきます。
ただ、個人的に気になるのは、各場面で大活躍する登場人物の年齢が自分よりずっと若い事です。
ここで、感情移入のハードルを感じました。(笑)
経営がうまく行っていない会社の経営者の方、または社員の方がこの本を読むと、「そう、そう!」と興奮して、ページをめくる手が止まらないと思います。
止まらない?そう、「止まらない」を英語で言うと"I can't stop."ですね。
”I can't stop."と言えば、やはり、杏里の「悲しみがとまらない」です。
この歌詞の中に「彼を返して!悲しみが止まらない。」と言うセリフがあります。
この一文で、何が起こったのかはっきりわかりますね。
取られちゃったんです。
彼氏を。
これは辛いですね。
辛すぎますよね!
そこの奥様、もし今、旦那さんを取られたとしたら「旦那を返して!悲しみが止まらない」と言えますか?
笑いが止まらないって言っている人はいませんか?(笑)
条件(お金)が良ければ喜んで!なんて言ってるんじゃないでしょうね?
今はそうかも知れませんが、この歌詞は、彼氏が人生そのものだった若い頃のお話だと思います。
この年代の女性はもう、彼氏なしでは生きていけないのです。
「彼氏を取られた」というのは、ひょっとすると、「大阪城を取られた」ことよりも、大事件だったかもしれません。
なぜならば大阪城を取られたら、別のお城を取ればいいですが、彼氏の代わりはいないんですよね。
その点をご理解下さい。
奥様方も昔は、そういうピュアな青春時代を過ごしていたという事を思い出して頂きましたでしょうか?
そのピュアな心は健在でしょうか?(笑)
ピュアな心にとって、彼氏を取られることは、とてもとても辛いことなんですね。
この辛さをご理解頂いただ上で、杏里の歌声をお聞き下さい。
サビは、最初のサビは13秒辺りになります。
悲しみが伝わって来ますね~
悲しみがとまらないでしょう~
飛ぶ鳥を落とす勢いであった杏里の絶頂期を、ご堪能頂けましたでしょうか?
この杏里の絶頂期は、著者がこの本の題材となる企業(コマツ)を顧客にした会社(三枝匡事務所)を起業した時期に重なります。
著者が日本企業の事業再生で燃えていた頃に、有線放送で流れていたヒット曲の1曲がこの曲になります。
なんとなく話が繋がったところで、本題に戻ります。
この本を読むと、著者の日本企業における経営の問題点や企業内の問題点などの捉え方、視点の高さ、緻密さに感心してしまいます。
この本には、経営再建のエッセンスが詰まっています。
経営者の方であれば今すぐ実践に役立てたくなるような事例が、至る所に敷き詰められています。
私が経営者であったら、「これは経営改革の宝箱や~(彦麻呂風)」と叫んでいると思います。(笑)
【2.本書のポイント】
多くの日本企業の社員は、戦略的なものの考え方が米国のビジネスマンより劣っている。経営リテラシー(戦略、マーケティング、組織改革など経営コンセットに関する読み書き能力)が低い。不景気を日本政治の貧困のせいにする人が多いが、責めるべきは自分の会社の改革の遅れなのである。社長こそが新しい考え方を探索し、それを提示し、そして社長が自ら行動しなければ何も起きないのだ。成功している「高成長組織」では組織が頻繁に変更され、社員の異動が日常茶飯事で、いつも社内はガタガタしている。あまり長い期間、異動のない人はかえっておかしいとみなされかねない。激しい議論は、成長企業の社内ではよく見られるが、沈滞企業では大人気無いと思われている。ミドルが問題を他人のせいにしたがるのは、ミドルが自分の裁量で解決できない問題があまりにも多いからである。これからの国際競争に対応し、戦略転換や経営改革をタイムリーに切れ味よく実行していくためには、日本企業の社内で「変化思考のリーダーシップ」が急いで育成されなければならない。改革者が有効な手を打つための第一歩は「事実の把握」だ。自分で組織末端を歩き回り、(ハンズオン)つまり自分の手で現場の細目に触れて事実を確かめなければならない。改革者は多くの社員に会い、新しい「ものの見方」を語る。そのストーリーがシンプルで正しいと思うわれるものであれば、改革者の言葉は強いメッセージ性を発揮し始める。元気な企業に行きますと、1つ上の階層の上司は、いつも配下の縦横の矛盾を自分で嗅ぎ回り、問題を自分でいち早く吸い上げます。組織内の綱引きに自ら先手を打ちます。そして明確な方針を自分で示します。商品別の全体戦略や、新商品導入計画が「開発→生産→営業→顧客」の一気通貫の連携で行われていない。だめな会社ほど開発テーマが多すぎる。全部やりきれるはずもないのに上層部があれもこれもと手間を増やすので、どれもはかばかしく進まない状態になる。総指揮官のくせに、マクロの戦略感覚が足りません。つまりマーケティングや全体戦略の感覚が足りないのです。会社全体で戦略に関するする知識技量が低い。戦略の創造性が勝負を分ける時代だというのに。私が推進する改革では、中心になるコンセプトが必要だと考えています。セオリーや原則論を外部から学んで初めて、ようやく内部の問題が見えてくる。現場改善のネタが尽き、社員が「改善疲れ」に立ったところで、日本企業の躍進は止まったのである。改革リーダーは、凝縮された時間軸の中でプロジェクトを立ち上げ、優秀な社員を極限まで追い込み、彼らの隠れていた能力を最大限に引き出そうとする。そのためには、最初の段階から組織のスピード感覚に強引でも変えていくことが必要なのだ。不振の大組織を蘇らせるにはそれが不可決のプロセスである。閉塞感の強い日本企業の組織が「攻めの文化」を取り戻すためには、高い見識の「プロフェッショナリズム」を外部から引き込みつつ、社員が「自らリスクに立ち向かう経営者的行動マインド」を持てるような心理循環を実践することが必要である。危機感はリーダーが人為的に作り出すものなのだ。成功する改革はリーダーの下でまとめられる「強烈な反省論」から始まる。会社の痛みを個人レベルまで分解することがカギである。自分の痛みとして危機感を抱いた人々は自分のために解決を図るべく動き始めるからである。シナリオ作り大切な事は①シナリオが論理的権威性に裏付けられていること、②分かりやすいストーリー性を持っていること、③改革リーダーが「熱い語り」を持って不退転の姿勢を示すことである。優れた改革シナリオは頭から「頑張り」を求めるものではない。仕組みによる強さのストーリーが明確なとき、気骨のリーダーの下で皆「頑張る」ことを始めるのである。先頭に立つ人の果てしない情熱の投入が必要である。「改革とは『魂の伝授』である。」「経営者にとって最も重要なのは『高い志』である。」
【3.本書の感想】
新しい時代になり、必要な経営改革の考え方や、手法は変わっても、「経営者にとって最も重要なのは『高い志』である。」という点に納得しました。
今、堀江貴文が、イケダハヤトが経営をした会社が業績を上げた時の、その「高い志」は同じだと思いました。
ただし、現在の経営を語る際、会社の組織や構造が、旧時代を代表する「メーカー(製造業)」をベースとしていても良いのでしょうか?という気がしました。
なぜなら、現在の日本社会の産業構造は大きく変化し、GDPの占めるメーカーの占める割合20%、雇用は17%と言われているからです。
これから新しく作るべき、新事業や新しい会社には、別の何かが必要である気がします。
この本はあくまでも、「メーカー」を意識した物語なのかもしれません。
メーカーの人たちにとっては、本書から学ぶ点は多いと思います。
この物語は、とてもよく出来ていて、参考にした部分を自社に導入できれば、その企業は上手くいくと思います。
ただし、その導入が難しいところに経営者の悩みが尽きないのだと思います。
この作品はとても、良い作品です。
経営者の方、経営参謀の方、特にメーカー系の方にはお勧めの一冊です。
V字回復の経営―2年で会社を変えられますか (日経ビジネス人文庫)
【4.関連書籍の紹介】
サムスンの隆盛の基礎を作った人は、日本でよく勉強していました。
経営者の方なら、ドラッカーの1冊や2冊は読まれていると思います。
そりゃアマゾンには、かなわんわと思わせる良書です。
中小企業経営者のスターが書きました。
有名コンサルの著書です。
言われてみるとそうりゃそうだという感じでしょうか?
市場の見極めが大事な理由が良くわかります。
定番ですが、お一つどうぞ。
京都のカリスマのお話です。
最後まで付き合い頂きありがとうございました!
