4月21日は開催します!
弘法市朝の様子です





弘法さんです。

東寺の番鳥、アオサギです。

桜と五重塔です。

桜と灌頂院北門です。

宝蔵前の蓮です。

月と五重塔です

弘法市にお越しの際は、是非、 新しくなった御影堂を是非ご覧下さい!

普段の東寺弘法市の様子をご紹介しますのでこちらでお楽しみ下さい。
東寺の弘法市とは、弘法大師・空海の命日(3月21日)にちなみ、毎月21日に開催されている東寺の縁日です。
当初は年に1回行われていたものが、1239年以降は毎月行われるようになったそうです。
全国的に知られる京都を代表する市の1つです。
1200店程が軒を連ね、毎月20万人近くの人々が訪れます。
特に骨董店は150店近くも出店しており、専門業者も参加しています。
他の市では少ない植木市など出店がバラエティ名所も見所です。
基本的には雨天決行となっています。
東寺の場所はこちらです。
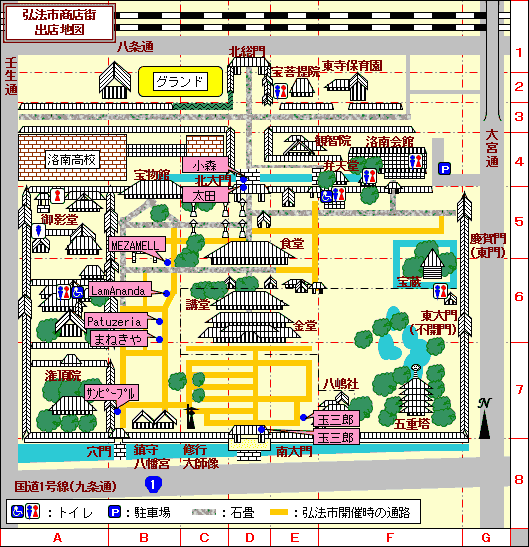
http://www.touji-ennichi.com/shop/images/smap.gif
こちらは、弘法市出店事務局作成の弘法市商店街出店地図です。
以前のものになりますが、なんとなく雰囲気を味わって頂ければと思います。

こちらは、南大門(重文/1601年/慶長6年)前エリアになります。
古着あり、骨董品ありで、弘法市を象徴する出店内容になっています。
今日は、一日中蒸し暑い中、沢山のお客さんで賑わっていました。
写真はふえ屋さん。これは、とてもレアですね。
沢山の種類の笛が売っています。
必要な人には必要なモノだと思いますが、残念ながら今日の私には必要ありませんでした。(笑)

こちらは金堂(国宝/1603年/慶長8年)前です。
このエリアも骨董品が多く、骨董品や古い着物が出す独特の香りが辺りに漂って独特な雰囲気を醸し出していました。
最近は、着物を着て観光地を回るサービスが増えてきた為、着物を来た観光客を多く見かけます。
着物を来ているのはたいてい観光客で、地元民はほとんど着ていないのは、何か矛盾を感じますが、一人でも多く、着物を着て京都の街を歩いてくれるのはとても良いことです。

こちらは引き続き金堂前です。
今日は、金堂の正面の扉が開放されています。
普段は有料エリアですので、入場券を購入した人しか、中を見られないのですが、今日は金堂に安置されている薬師三尊像を拝む事ができました!
薬師如来は坐像ですが約3Mの高さがありますので、かなり迫力があり、祈りを聞いていただけそうな気がしました。
◆薬師三尊像
・薬師如来坐像(木造/重文/1603年/慶長8年)
・日光菩薩立像(木造/重文/1603年/慶長8年)
・月光菩薩立像(木造/重文/1603年/慶長8年)
仏師康正の渾身の名作です。

秋は、こんな感じです。

秋の弘法さんです。

秋は、紅葉を楽しみながらの弘法市です。

奥の方に金堂と講堂が見えます。

こちらは、紅葉と五重塔です。

秋って感じですね~

さて、引き続き金堂前エリアです。
骨董品が多いエリアとなっていて、いるものだか、いらないものだか、よくわからないものも沢山売っていました。(笑)
そういう骨董品をガラクタという人もいて、あながち間違ってはいないななんて思いました。

こちらのように、東洋を感じさせるものは、欧米の人に興味を抱かせる様です。
ちょうど、奥においてある兜を、中国人観光客が興味あったらしく、値段交渉をしている所でした。
写真で見ると大きさが分からないと思いますが、こどもの日に飾る、ガラスケースに入ってそうな感じのものです。
8千円でどう?なんて声が聞こえたような気がしました。

これ、値段の検討が付きませんよね。
見た感じ、定価は高めに設定している感じがしました。
夕方に交渉したら、安くなるかもしれませんね。(笑)

こんな感じものがたくさん販売されています。

何か必要そうなものは見つかりましたか?(笑)

こちらは、掛け軸です。
おそらく、良い品も売っていると思いますが、観光客が高いものは買わないと考え、お手付頃価格のものを用意しているように見えました。
観光旅行に来て、高価なニセモノを掴まされたら大変なので、そうそう高価なものは売れないんじゃないかと勝手に思っています。
でも、中国人の大金持ちなら、値段を気にせず、買って行くかも知れませんね。

欲しいものありますか?(笑)
うちは部屋が狭いので、置けないですし、収納する場所もありません。
という訳で、スルーしました。
ちなみに、お店の人からガンガン売り込まれる事はほとんどありません。
興味を示せば、売り込んで来るとは思いますが、出店者側からの売り込みは全体的にゆるい感じでした。

こちらは、弘法大師像です。
弘法市という事もあり、お参りされる人で賑わっていました。
普段はここまで賑わっていないので、お大師さんも大変喜んでいるのではないかと思います。

このあたりから、商品が変わってきます。
こちらは、手作りの時計を販売されています。
お求めやすい価格で、展示もおしゃれな感じですね。

こちらは、手作りの木製のペンダントです。
値段が1個2,000円となっています。
高い、安いはそれぞれ思いがあると思いますが、なかなかおしゃれなアクセサリーだと思います。

こちらはお椀類を販売しています。

こちらは、焼きそばのコーナーです。
意外に思ったのは、いい具合に食べ物のお店を配置している所です。
そして、その横には食べるスペースが設けられてあったりして、疲れたら、何か食べつつひと休憩。
そんな感じの心配りがされていました。
今日は、暑かったので、かき氷がよく売れていました。
値段はほとんどが300円でしたが、その店によって、量や見た目も全然違うので、当たり外れがあるんだな~と思いました。

ちなみに冬になると、おでんなんかも出てきます。

寒い日は、うどんが欲しいですね!

こちらは手作りのカバンやさんです。
中央の深緑のカバンに代表されるように、値段は1万5千円前後のカバンが多かったです。
値段もデザインもとても良かったです。

こちらは、御影堂エリアから見た東側の様子です。

こちらは、北大門付近です。
歩き疲れたときには、コーヒーで休憩しませんか?

こちらは、可愛らしいデザインのTシャツです。
 こちらは、壁掛けでしょうか?
こちらは、壁掛けでしょうか?
日本旅行のお土産にはピッタリですね。

こちらは櫛笥小路、東寺の北側エリアになります。
櫛笥小路は、平安時代からその道幅が変わっていないと言われています。
歴史的に重要な小路です。

その歴史的重要な舞台にこの表示。
「ヤケクソ。」「決死の決断」と書いています。
よく見ると、半ズボン、安いですね!
これなら売れるでしょう!
私は買ませんでしたけど。(笑)

他のお店も安いですね!😊

こちらは観智院(1359年/延文4年)です。
こちらの中には、宮本武蔵が書いたと言われる鷲の図や、立派な客殿などの国宝があり、期間限定で公開されます。
とても、上品な客殿です。
機会がありましたらぜひ、御覧ください。

大判焼きです。
名物って、どこの名物なんでしょうね。
これは普通よりも大きめで値段は1個120円と、かなり良心的な価格でした。
味は、庶民的な味で、美味しかったです。

こちらは、北総門横の不動明王です。
毎日信者の方が、熱心に水掛けをされています。

こちらは、出店で販売されていた蓮の花です。
とてもきれいですね。

こちらも同じく、白の蓮の花です。
とてもきれいでした~

こちらは宝蔵(重文/平安時代)の周りの堀に咲く、蓮の花です。
こんなに沢山の蓮の花を見たのはここ、東寺が初めてです。
見るたびに、茎の高さが伸びて、花の位置がどんどん高くなって来ています。

極楽じゃ~
そんな言葉が出てきそうな、素晴らしい風景です。

もうそろそろ、蓮の花はピークかと思いましたが、まだまだ行けそうですね。

小野道風ゆかりの柳の下のカエル石です。
ピンぼけで申し訳ございません。
カメへん、カメへん。(関西風)

こちらは東大門付近になります。

食べ物や植物を販売しています。

鉢類です。

お花がキレイですね。
という訳で、一通り回って見ました。
当初、ガラクタ市かと思っていましたが、いろんなモノが出品してあり、見て回るだけでももとても楽しかったです。
海外の観光客もとても多く、皆さんいろんなものを買って楽しんでいました。
飲食系は、焼きそば、たこ焼き、ベビーカステラ、鯖寿司、鮒寿司、漬物、ちりめん、かき氷、コーヒーいろんなモノが売っています。
特に飲食物の料金はお手頃価格ですので、気軽に楽しめると思います。
毎月21日に開催している弘法市、機会があればぜひお越しください!
旅行につきものはお土産ですね!
東寺や旅先でお土産を買うのは楽しいですね。
でも、職場やご近所さん分は旅行前に注文しておくと、観光に使える時間と体力をセーブできますよ!
実は、地元の方にもリピータが多く、とても評判の良い所がこちらです。私は、いつもここで京都土産を先に注文して送っていますので、手ぶらで楽ちんです!
東寺の基本情報は、下記を御覧ください。割としっかり。
東寺に行ったら是非食べておきたいこの餃子!
最後までお付き合い頂きましてありがとうございました!
【追加】ちなみに2022年1月21日は雪景色の中での開催でした!

山水画の世界ですね。

積雪の中、屋台が準備されています。

準備中ですが、商品にも雪が積もっています。

今日は、雪帽子の弘法さんです。

今日は大丈夫でしょうか?

すこしでも温かいモノ食べて、温まりましょう!

雪の東大門です。