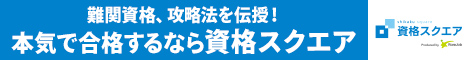【1.本書の紹介】
この本は、脳の基本的な動きをベースにして、学習、特に覚えることに対して、いろんなヒントを紹介しています。
最近は、脳科学が進んでいるため、私たちが子供の頃に比べると、効率的に学べる方法がたくさん分かってきています。
例えば、昔は、4当5落などと言って、4時間睡眠は合格し、5時間も寝ていると不合格になるなんて事がよく言われていました。
最近は、逆に、しっかり睡眠を取った方が記憶の定着には良いという事が言われています。
こういう事を知っているのと、知らないのでは行動が全く違ってきますよね。
間違った常識を修正する為にも、常に、最新の情報を得たいものだなーと思いました。
【2.本書のポイント】
勉強する環境には音楽などの何かがある方が、何もない環境よりも良いということがわかった。「共感覚」複数の種類の感覚で恐ろしく鮮明に感じ取る能力を表す。例えば、音を聞いたら形や色を感じ取り、文字をみれば、味や匂いを感じ取るという具合。単純に覚えるものによって場所を変える。今日少し勉強し、明日また少し勉強したほうが、一度に全部するよりいい。外国語の語彙や、科学の定義など、事実に関する情報を習得して記憶にとどめたいなら、最初に勉強した1,2日後に復習し、その次は1週間後、その次は1ヶ月後に復習するのが最適だ。同じことでも、環境や日を変えて覚えると、他のこととの関連づけが生まれ、頭の中に深く刻み込まれる。本の一節を暗記したいなら、20回読むよりも、暗唱を試みて思い出せないときに本を開くということを織り交ぜながら10回読む方がいい。自分で自分をテストすることが本番での発表に大きく影響することを実証した。学んだ事を自分自身や自分以外の誰かに説明するという行為は、非常に効果の高い学習だ。知らないこと、混乱している部分、忘れていたことを、あっという間に明らかにしてくれる。問題解決4つのプロセス。準備→孵化→ひらめき→検証ウォーラスの最大の貢献は、「孵化」の段階を定義したことにある。彼はこの段階を、脳が休息し「一から考える状態」に戻るだけの受動的な段階だとはとらえず、この間に、問題を意識はしないが、無意識で問題と向き合い続けていると考えた。無意識下の頭のなかでは、脳が様々な概念や考えと戯れながら、上の空でジグソーパズルをするかのように、ある考えを脇にどけたり、複数の考えを一つにまとめたりしているのだ。創造性の飛躍は、ストーリーやテーマに浸っていたあとの中断時間に起こることが多い。基本的なニーズや動機が、それを満たすのに役立つものを周囲から知覚する力を増大させる。喉が乾いているという状態が、飲み物につながる何かを周囲から獲ろうとする脳内ネットワークを活性化させた。目標の達成に向けて行動を起こすとそれが最優先事項となり、近く思考、言動が突き動かされる。大きな仕事を抱えた時は、できるだけ素早く着手し、行き詰まったら立ち止まる。投げだすのではなく抽出を始めるのだと自信を持って中断すれば良い。山を乗り越える前にそれが中断したからといって、その仕事が完全に止まるわけではない。止まっているように見えて止まっていない。これが抽出の第1段階だ。それに続いて、関係する情報を紐づけする第2段階が始まり、身近なところから関係する情報を収集する。そして、第3段階では、入ってきた様々な情報について自分の思いに耳を傾ける。抽出はこの三つの要求で決まり、この順番で起こる。学習中に関連性はあるが、違う何かを混ぜることインターリーブと呼ぶ。インターリーブの本質は、能を予期せぬことに備えさせることにあるように思う。知覚学習は能動的な学習。わたしたちの目は自分のためになる何かを常に探している。PMLは知識や技術を習得するのに役立つもの。訓練されていない目には同じに見えるが、実際には区別または分類できる何かが学べる。知覚学習のいいところは、自動的に学習が始まり、知覚学習のシステムから自ら学ぶ対象に波長をあわせるところにある。何も考えていなくても知覚は学習しているのだ。自分の知識をより深く能に刻み込むためには、自己テストや間隔を開けた学習のように。思い出すのに多少の苦労がともなう事をする必要がある。
【3.本書の感想】 
抜き出したポイントをみると、それだけではわかりにくい感じがしますね。
この本には、沢山の事例が出ていますので、それを見ると理解しやすいのですが、
抜き出すと理解しづらくなってしまいました。
記憶に関して言うと、左脳に覚えさせるのではなく、右脳に覚えさせるのが最強だという事が書かれています。
右脳、つまり、文字で覚えるのではなく、イメージで覚えることが長く忘れないコツだそうです。
人の顔を思い出しても、名前が思い出せないことがよくありますね。
これは、典型的な覚え方の違いですね。
顔はイメージで、名前は文字。
日本語は象形文字なので、アルファベットに比べると文字を見た際に、意味は推測できます。
しかし、名前となると、文字のイメージとして覚えるのではなく、もろ、名前として文字で覚えてしまうので、記憶から消えてしまうのでしょうね。
名前を覚えるにしても、少々の努力は必要だと書いています。
私も、子供の友達の親と知り合いになっても、名前をよく忘れます。
ですので、自分の名前を呼ばれても、相手の名前を呼び返せません。(笑)
真面目に、覚えることをしないといけないって事ですね。
いろいろ為になることが書かれていますので、是非読んでみて下さい!
【4.関連書籍の紹介】
この本を読んで走り出す人多数!
スマホは悪いです。(笑)
脳は大事にしましょう。
頭が良くなります!
最後までお付き合い頂きありがとうございました!